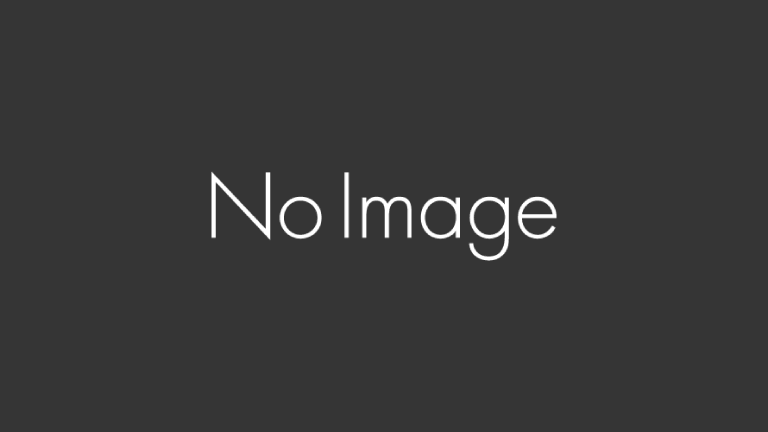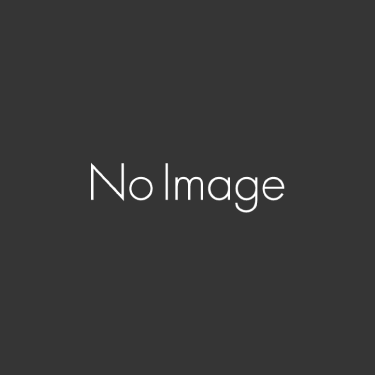テーマと内容だけはずっと頭にあるものの、整合性のある文章にするのがなかなか難しくて「書かず放置」「書いたのにまとめず放置」なんてのを繰り返してきた話題を、多少なりともまとまった状態で垂れ流していこうという久々の感じです。
ほぼほぼブレインダンピングですが文体自体は他人にも読めるようにしたつもりです。
名前というものの力
例えば、某宇宙的小説作品の登場人物であるが「ヘルムート・レンネンカンプ」という名前が出てくると、
「何か強そう」「厳めしそう」というイメージが、少なくとも私的には浮かんでくる。「アンネローゼ・フォン・グリューネワルト」という名前が出てくると、身分の高そうな貴婦人のイメージが湧いてくる。
名前というものには、それだけで読み手に何らかの先入観を与える便利な記号でありえるわけだ。
漫画やアニメ、ライトノベルなどにおいてはもっと極端に、名は体を表すと言わんばかりに「こいつはこういうやつだ」と直接的にわかる名称にし、イメージを認知させるツールとして利用されることも多い。例えばネコ型ロボットが登場する某国民的作品にもその傾向がある。というかあの時代の漫画作品には特にその手の名称が多いのか。
他にも、如何にも資産家などの御曹司っぽい苗字として「〇〇院」などという名前が用いられたり、「なんとなくそういうキャラ」ということを分からせる名前付けは、多かれ少なかれ一般的に行われている名づけの方法である。
洋風のカタカナ名の例だととりあえず「フォン」を着けると貴族という設定にしやすかったり、セカンドネーム以下をふやしたら由緒正しそうな名前になったり。そういうとこで先入観を与えるキャラ付けが行われる。
名無したちの物語
その便利なツールを敢えて「使わない」物語というのは、1つの異端であるともいえる。日本の文学小説において、物語のはじめから終わりまで主人公の名称が不明のままであり、「私」などの代名詞または無機質な記号的表記のまま表記され続ける作品がある。
主人公が「誰」かというのは物語の中の概念では語られない。書き手の頭の中では確かに「誰か」であるのかもしれないし、ないのかもしれない。比較的新しいエンタメ文学だとそうそう存在しない現象だと思う。主人公がどこの誰かわからない「私」である物語は。
そういう作風は、日本の純文学の1つの特徴かもしれない。なお、海外の物語には詳しくないので触れない。これは必ずしも私小説と一致するものではない。例えば夏目漱石の「吾輩は猫である」「坊つちやん」「こころ」なども主人公に固有名詞は与えられていない。何なら主人公以外の登場キャラクターであっても何らかの普通名詞で呼称される。
例えば「坊つちやん」の主人公は、ありふれた存在である田舎の新任の教師。そういう「名無しA」とその周囲の人物たちを取り上げて、その関係性や内面を描いてみる。私小説ではないが、フィクションなりに「それっぽい体裁の何か」であるともいえる。
この手の文学のすごいところは「ありふれていそうな名無しの誰か」に対して何らの先入観や余分な情報を与えないままに魂を吹き込み、生き生きと描き切る事である。何とはなしの「共通認識」に頼らず、すべてを著者の筆力で乗り切る自負のようなものだろうか。一応、「当時の日本における当たり前」という共通認識の上に成り立っているのは確かだが。
インスタントノベル
上記のような、「名無し」主人公の作品が時代とともに廃れていったのは、必然的に書き手のスキルも読み手の読解力も要求されるからなのかもしれない。というか、むしろ年月ととともに逆方向に加速して言っているように見受けられる。
例えばライトノベルで近年量産されている「異世界転生」ものの作品。プロの仕事ではないものが多々あるのはともかくとして、共通認識に頼った1つの典型例であるといえる。つまり、読み手の能力を限りなく下限に見た上で、書き手の労力を限りなく削減することによって成立する文化である。
現代日本において「読み手に取って常識」になった用語を用いることで、「読者層にとっては一切の説明がなくてもで分かる」というインスタントな世界観である。
その典型例としては、ファンタジー風な世界観の設定がある。適当にRPGっぽい要素を入れたらなんとなくわかってくれる。例えば「ダンジョン」と書けば、「なんか魔物が出そうな洞窟や地下エリアなどの隔離空間」なんだなって。まかり間違っても「地下牢のことかー!」とはならない。
ついには「レベル」だの「スキル」だの言いだすのはやりすぎというかゲーム的過ぎるフシは存在するが…。
こういった用語を拝借し、一切の余計な説明を省き、なんとなくわかる世界観で深く考えずに物語を楽しめるというのは、特に現代社会において生き疲れた人々にとって消費しやすくありがたい存在なのかもしれない。理不尽なんて現実で十分味わっているからこそ、何となくうまく行く別世界の話が聞きたい、と。
「難しいことはいらない」「ストレス発散したい」「細かい説明なしで分からせたい」。あらかたのアングラ好き日本人が「言わなくても分かる」ものを並べて世界観を不要にするっていうのが近年の量産ラノベの傾向といえる。
ミームの変遷による創作の変異
先ほどのダンジョンの他にも例えば「スライム」というと、真っ先に思いつくのがかわいらしいい謎の生き物である人も多いかもしれない。そうでなくてもモンスター的生物のことを想像する人はかなり多くなっているだろう。
しかしスライムとは本来はゲル状の物質のことだし、スライム形状の何かが動き出すという事案自体がもはやRPGなりファンタジーの世界。
もちろんミームというものはそうやってうまれていくわけだけど、それを最大限に生かしたのがライトノベルの主流だと思うと、そもそも量産型じゃなくなることが難しくなってくる。差別化は細かな設定や演出で行われることになる。多くの作品は商業化されたとしてもインスタントに消化されていく。もちろん突出したものも出てくることは出てくるけど。
そりゃあ小麦粉と砂糖と卵とバターだけつかって料理作れって言われたら、似たものができやすいのはしょうがないよねって。
現代に置ける“名無し”の物語
そんな中、比較的近年のもので星新一さんのショートショートはそもそもが「どこにでもいそうな誰か」の物語であること売りであるというイレギュラーな立ち位置である。
N氏だのS社だの、記号化された人物や組織によって成立する物語。敢えてそれらに色を付けないことにより、内容や主張に特化した物語。未来のどこにでもいる人物たちの物語。
例えば太郎とかハナコとかでも良いと思うかもしれないが、それだと微妙に色がついてしまう気がする。なぜならあの物語はそもそも国がどこか(現代のような国家が存在するか)も不明だし、そういう背景は無いものとして描かれている。
そうした設定は、1話完結するには恰好のものなのだろうと思ったり。特に共通認識を必要とさせる設定には向いてないのが1話完結ものとも言えるし。
“名前”がテーマの物語
現代(戦後はるか先という意味での)の物語の中で「名前」をテーマにしたものとして印象深いのが「火星物語」。ラジオ発で最終的にゲームとしても発売されたそれは、名づけという現象が個人のアイデンティティに関わるものであるというスタンスで語られている。
「命名の儀」を行われるまでは「少年A」「少女Y」などと記号で呼ばれ、儀式が終わった後は国から定められた仕事をこなしていくことになる。その中で社会にとって危険と判断された存在はAIチップを脳に埋め込まれ、機械的に生きるだけのロボットのような存在になる。
そんな中で主人公たちは、そういった国のあり方に賛同せず、「自分で自分の名前を付ける」という行為を通して抗っていき、自由を取り戻そうと奮闘していく。
名前のほかにも興味深いテーマはいくつもあるけれど、やっぱり最も印象深いのはそこかな、という感じ。
「名は体を表す」という言葉もある通り、人や動物に対しての名づけ(または名付けない)という行為は大きな力を持つというのが個人的な実感です。言霊なんて思想もあるけど、そういう話以前に。
成り行き任せのような文章ですが、まだまだ書きたいこともあるので記事を分けて投稿するかもしれない。かもしれない。