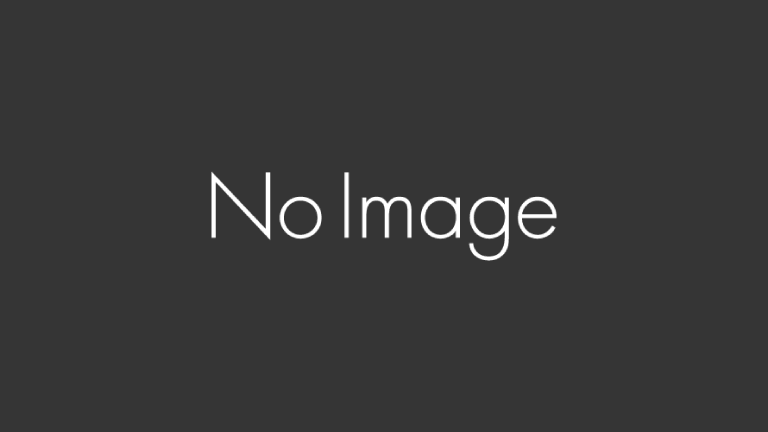投稿日 2023年9月12日 最終更新日 2023年9月12日
今回はブックレビューと雑記を混ぜた感じの記事です。
書籍概要
「砲兵」から見た世界大戦: ――機動戦は戦いを変えたか(古峰文三)
この本は、第一次世界大戦から第二次世界大戦を中心に、「砲兵」という兵科の在り方を軸とし、陸戦の戦略戦術の移り変わりが解説されている書籍です。
戦争の経過や兵器のスペックのみではなく、各国のドクトリンや開発・生産状況に基づいて「砲兵」のあり方がどのように変化していったかを見ていくことができる、なかなか独特な書籍となっています。
生々しいのは予算の配分によって開発や生産が停滞した側面など、開発技術や部隊能力以前の問題が大きく語られている点。こと戦争においては指導部の能力のみが勝利を左右するかのような(〇〇が無能だったから負けた、あそこでこうしていれば勝てた、etc…)語られ方をしがちですが、近現代戦という総力戦においては「銃後」の状況がよりいっそう重要になっていることを改めて浮き彫りにしてくれます。
おおまかな全体像
●WW1が始まるころまでは歩兵の進化に砲兵が追い付けなかった。
●しかも塹壕で鉄壁防御されて守りメタだけ異様に強くなった。
●がんばって砲兵運用するには航空支援(敵配置読み取りから弾着から何やら)が必須だし、それでも塹壕は破れず砲弾消費は激増。
などなどがあの泥沼の総力戦を呼び込んだとのこと。
機動戦についていけないから軽砲化が進むも、まともに運用するには歩兵の正面から被弾覚悟で打ち込むのが砲兵のメタになるというなかなかとんでもない状態からのスタートだったので、兵科としての独自性を取り戻すまでに長い年月がかかります。それに対して、逆にドイツなどが重砲主義に回帰するも、やはり塹壕の防御メタが進化しすぎていてなかなか破れない。
そして戦車の参戦後、「準備砲撃の代わり」を戦車による鉄条網の除去などで補い、砲兵は縦深制圧の方に特化することで反撃を抑止しする工夫が行われ、結果的に成功とはいかなかったもののメタの転換というか、各兵科の連合運用が改めて見直されるきっかけとなったのがカンブレーの戦い。
これを転機に、一般的にいわれる「機動力」のみではなく、「火力の機動性」という概念も突き詰めていくことで、砲兵は次第にその真価を発揮していくようになりました。
第一次世界大戦末期の縦深制圧によって「殺戮の象徴」と誤解され(実際には死者を減らす意味での司令部等の無力化が目的であった)、戦間期にその発展を忌避された砲兵や自走砲のあり方、そしてその結果、一次大戦で得られた戦訓を全く生かせないまま始まってしまった第二次世界大戦。
そしてその中で再び注目されていく火力主義による砲兵運用や突撃砲の誕生、そして最終的には戦車と同様の運用を行われるようになったり、これまでの運用目的であった「火力支援」というサポート枠から「砲兵中心の諸兵科連合的編成」によるメイン火力へと進展していく。
さらには戦線悪化によって本来の運用を「したくてもできない」から雑に扱われるようになったドイツ軍突撃砲部隊があったり、単純なスペックや指揮官の能力では把握することができない「国家の都合に左右された砲兵のあり方の変遷」を見て取れるのが非常に興味深い。
このように砲兵の在り方は、野砲や自走砲の兵器開発やその運用といった単純な構図ではなく、各年代の環境に応じて「全く違う役割」をその時々で担わされ、三歩進んで四歩戻るようなことも多々ありながら、試行錯誤の運用が繰り返されてきたのだという様が描かれています。
ソ連に関しては、本文中にある「無尽蔵な兵力で無謀な突撃を繰り返し、その後ろからは督戦隊(監視部隊)が友軍を射撃するという野蛮極まりない姿がソ連軍の典型だと思ってしまうと、その戦術の持つ基本に忠実な性格や信じがたいほどの丁寧さを理解することができなくなります。」という一文が、個人的には非常に印象的でした。
ジャンル分け考察の限界とビッグデータ化
つまり、「砲兵とはこういう兵科で、このような役割と目的で運用された」とか、「自走砲とは戦車とは違う運用のために作られた兵器で、砲兵に属するものである」などといった解釈では、戦争のほんとうの姿を知ることはできない、ということを、砲兵という兵科はありありと見せつけてくれているわけです。
何しろ本書の中で自走砲の役割は、野砲の上位互換から実質的に戦車と同じ運用まで、多種多彩な役割を強いられていることが描かれているのですから。「自走砲はあくまで自走砲で戦車ではない」という考えに固執すると、絶対に見えないものがあります。
これ、20世紀の学術や研究のあり方全般に存在していた問題だと思うんです。「あれはA、これはB」といった風に何でもかんでもジャンル分け、カテゴライズを行って区分し、その区分ごとに考察する。
そして、「どちらともいえない」個体がでてくると、あれはここがこうだからAだ、いやあそこがああなってるからBだ、などと区別することそのものが目的になってしまう不思議な議論が繰り広げられる。何というか、オタクの趣味考察による言い争いのような様相を呈していると言っても過言ではありません。
歴史考察においても、20世紀においては史学と考古学、社会科学がそれぞれ個別に研究し、個別に考察し、個別に発表するという在り方により、ほんとうの全体像が見えにくいという側面があったということです。
しかし21世紀になると空気が変わってきたような気がします。特に日本史の研究において顕著に感じられますが、本人の専門以外の研究結果も引用しつつ、分野横断的な研究考察を行う例が散見されるようになりました。近年の日本歴史学の進展は著しいと思います。
また、旧来はある種の象牙の塔と化していた医学でも、量子力学という別ジャンルの要素を取り入れた研究が進んでいます。その中では、従来はオカルトと言われていた物事にも、きちんと検証すれば役立てられるものもあることが示されつつあります。スピリチュアルと脳科学の結びつけなどもそうです。
すなわち、分断による研究の時代は終わり、これからはカテゴリに囚われずないビッグデータの活用こそが新たな知見を生み出す鍵になりつつあるのではないかな、と思うわけです。そうした思考の在り方の1つとして、砲兵の在り方の「定まらなさ」はまた一味違った面白味があるといえるでしょう。
現代における名将の定義
さて話は変わりますが、私の見解としては、前近代と近現代において「名将」の定義が大幅に変わったという意識を持っています。近代はどちらかというとまだ前近代の雰囲気も残してはいると思いますが、現代になると全く異なるという認識。
前近代では「双方が最低限やることをやっている中で、相手の意表を突いて勝利をもぎとる」というタイプの指揮官が名将とされることが多い。そのため圧倒的劣勢を覆す戦争というのも多くみられ、「加点法」の名将評価になりがちです(なお、堅実で目立たないタイプの指揮官も再評価されるようになってきていることは付記しておきます)。
例えば、三国志で有名な中国・後漢末期の「官渡の戦い」において敗北した袁紹の指揮は基本的には正攻法で、必ずしも名将とは言えなかったものの決して無能であったとは言い難いものでした。盤石な攻めだからこそ曹操も対応策が見つからず、荀彧に泣き言を言ってたしなめられたりするわけです(異見があるかもしれませんが私の解釈ではそうなります)。
しかし、戦線の長期化にともない、内部の権力闘争による悪影響や、それに乗じた曹操からの奇襲によって「相手が悪かった」負け方をしたという解釈ができます(もちろん統制力のなさは弱点ですが、あくまで純軍事的な意味合いで)。「もっとうまくやれば勝てた」は拙劣さによるものではなく、プラスアルファの戦略戦術が採れなかったことに起因するわけです(そして烏巣の失陥という1失策からの寝返り多発で負ける)。
一方、近現代では戦場のマクロ化により「圧倒的劣勢を覆す奇策」というものが成立しづらくなっており(そのため「奇襲」という言葉のニュアンスも大きく変わりました)、近現代では「教科書通りにミスなく指揮統率でき、相手のミスに乗じることができる」タイプの指揮官が成果を残している印象が非常に強いです。
そもそも、その「教科書通り」の正解がわからず各国のドクトリンすら右往左往するからこそ、国家も指揮官もミスまみれになって比較的ミスの少ない方が勝つという「減点法」な感じです。
ドイツのマンシュタインやソ連のジューコフなど、世界大戦で成果をあげた指揮官は、多かれ少なかれそういう傾向を持っていることが多いという認識(あくまで前近代と比べると)。
プロ野球のピッチャーに「計算できる」という概念がありますが、あんな感じです。「安定して試合を作ってくれる」「大体これくらいの失点で抑えてくれる」という感じのアレです。期待値を満たしやすい「計算できる将軍」が活躍することが多いのが近現代戦。
もちろん、逆張りギャンブルで大勝利した将軍や相手の裏をかくことに傾倒した将軍が全く居ないとは言っていません。全体的な傾向の問題です。また、誰が名将で誰がそうでないかは議論が分かれるところだし、どういった立ち位置で活躍したかも千差万別なのでその話題は措いておきます。
このように、前線での戦争指揮もある意味で「やってみないと分からない試行錯誤」「誰もが間違えるのでミスが少ない方が勝つ」といった状況が現出します。そしてそれは戦場にのみならず、戦争指導部や生産体制、ひいては国家そのものの方針だって同様であったといえる、というところにつながっていくわけです。
まとめ
ともあれ、近現代の戦争において人類は、最新のテクノロジーを随時更新しつつもそれを必ずしも使いこなすことができず、ドクトリンや運用方法についても多くの失敗を重ねて何とか1歩ずつ進んできました。
しかも多くの失敗や犠牲の上に得られた「答え」も、何かのきっかけに大幅に退化してしまう(その原因が単なる感情論だったりするのが如何にも人間らしい)。そんなパターンが繰り替えされているという印象を私は強く持っています。
そして本書で取り上げられた「世界大戦における砲兵」はさながらその象徴のように、進歩したり退行したり右往左往したりする様をまざまざと見せつけてくれていると思うわけです。そういう意味も含め、非常に興味深い書籍だと思うので、興味があればぜひ読んでみてください。
なお、この文章を読めばお分かりかと存じますが、おそらくこの書籍は教養としての世界大戦に関する知識を多少なりとも蓄えている人に向けられたものではないかな、と思います。何も知らない人の入り口にするにはやや難易度が高いかも。